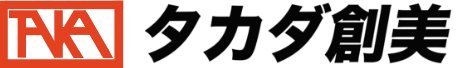NEWS & COLUMN
お知らせ&コラム
-
2026.01.06
お知らせ
コラム
【公式LINE開設】現場写真を送るだけで簡単見積もり!チャット相談はじめました
いつも株式会社タカダ創美のホームページをご覧いただきありがとうございます。 この度、よりスムーズにお客様のお困りごとを解決するために、LINE公式アカウントを開設いたしました! これまで「電話だと現場の状況を伝えにくい」「メールだと写真の添付が面倒」といったことはありませんでしたか? これからはLINEを使って、普段の連絡と同じ感覚で気軽にご相談いただけます! ✅ タカダ創美の公式LINEでできること 1. 写真を送って「スピード概算見積もり」 「テントが破れた」「工場の間仕切りを新設したい」 そんな時は、スマホで現場の写真を撮って送ってください。現場調査の前に、概算の費用感や施工の可否をお伝えすることができます。 2. 図面のやり取りもスムーズ FAXやメールを使わなくても、PDFや図面データをLINEでそのまま送信可能です。もちろん紙に書いた手書きの寸法入りの図をスマホでパシャリと撮って。そのまま送っていただいてもOKです! 3. 営業時間外でもメッセージ受付OK 日中は現場で忙しい方や、夜間に急に思い出した時でも、LINEなら24時間いつでもメッセージを送っていただけます。(※返信は翌営業日に順次対応いたします) 👇 友だち追加はこちらから! 以下の友だち追加ボタンを押すか、QRコードを読み取って「株式会社タカダ創美」を友だち追加し(友だち追加しないとトークできない仕様なのです、申し訳ありません)お気軽にお問い合わせください。 皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。 -
2026.01.01
コラム
謹賀新年
あけましておめでとうございます 皆様には 健やかに新春を迎えられたことと お慶び申し上げます 旧年中は ひとかたならぬご厚情をいただき ありがとうございます 本年も 変わらぬお引き立ての程 よろしくお願い申し上げます 皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます -
2025.12.15
コラム
【後編】テント倉庫とプレハブ倉庫の違い|断熱・耐候性・防犯性で選ぶならプレハブ倉庫
前編では、テント倉庫が強い「コスト・納期・柔軟性」について解説しました。後編となる本記事では、プレハブ倉庫が優れている性能面 を中心に比較します。 1. プレハブ倉庫の基本構造(おさらい) ・鉄骨に金属パネル(折板・サンドイッチパネル)を取り付けた構造 ・高い耐風性・耐雪性・断熱性・防犯性を持つ ・建築基準法の建物として扱われ、恒久利用に最適 一方のテント倉庫は膜材による簡易構造で、柔軟性・コスト性能が高い反面、 断熱・防犯性では劣ります。 2. 断熱性の違い — 温度管理が必要ならプレハブ ▼ テント倉庫(標準では断熱が弱い) ・膜材1枚構造のため外気温の影響を受けやすい ・夏場の内部温度が上がりやすい ・冬は冷え込みやすい ※遮熱膜材・内張りなどのオプションで改善可能です。 ▼ プレハブ倉庫(断熱性能が非常に高い) ・ウレタン入りサンドイッチパネル ・断熱屋根パネル これらにより、 ・暑さの侵入を抑えやすい ・冬場の暖房効率が高い ・全体的な温度管理が容易 食品・精密部品・化学製品など、温度管理が必要な倉庫はほぼプレハブ一択です。 3. 耐候性 — 風・雨・雪に対して強いのはプレハブ ▼ テント倉庫 テント倉庫は軽量鉄骨と膜材を組み合わせた構造で、地域の風荷重・雪荷重に合わせた設計によって必要な耐候性能を確保できます。 ・仕様や膜材の選択によって、風・雪への対応が可能 ・膜材は経年で劣化するため、定期的な張替えで性能を維持 ・柔軟な膜材の特性上、強風時に動きが出ることもあるが、構造上の想定範囲 用途に応じて性能を調整できるのが、テント倉庫の特徴です。 ▼ プレハブ倉庫:構造的に耐候性能が高い プレハブ倉庫は、鉄骨に金属パネルを組み合わせた建築物で、構造自体が“風・雨・雪”への耐性を高めやすい点が特徴です。 ・鉄骨フレームが強固で、外壁パネルも高い剛性を持つ ・気密性・遮水性に優れ、外気の影響を受けにくい ・積雪地域や強風地域など、環境条件が厳しい場所でも採用されやすい(※必要に応じて地域の基準に沿った構造検討が行われます) こうした構造上の特性から、長期利用を前提とした恒久的な倉庫や、屋内環境を安定させたい用途に向いています。 4. 防犯性 — 決定的な違い ▼ テント倉庫の弱点 膜材は一定の強度はあるものの、刃物で切られてしまう という構造上の弱点があります。 高価物保管には不向きで、防犯カメラや赤外線センサーの追加が必須になるケースもあります。 ▼ プレハブ倉庫(防犯に非常に強い) ・外壁が金属製 ・侵入には工具+大きな音が必要 ・建物としての“固さ”がある → 防犯性能はプレハブが圧倒的に高い 5. 用途別の最適な選択(性能面を重視する場合) ▼ プレハブ倉庫が向いている用途 ・温度管理の必要な倉庫(食品・精密機器など) ・高価物保管 ・防犯を重視する現場 ・台風・積雪などの気象リスクが高い地域 ・事務所併設施設 6. まとめ — 性能面を重視するならプレハブ倉庫 ・断熱性:プレハブが圧倒的 ・耐候性:建築物として高いレベル ・防犯性:金属パネルで侵入が困難 ・長期利用:長寿命で維持しやすい 総合的に、性能・耐久・防犯まで求めるならプレハブ倉庫が最適 といえます。 倉庫設置をご検討中の企業様へ 本記事が倉庫選びの検討にあたって参考になれば幸いです。 → 前編では、テント倉庫が優位な面を詳しく解説しています。 【前編】テント倉庫とプレハブ倉庫の違い|コスト・納期・柔軟性で選ぶならテント倉庫 テント倉庫の導入をご検討の際は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。用途・予算・納期に合わせ、最適なプランをご提案いたします。 -
2025.12.15
コラム
【前編】テント倉庫とプレハブ倉庫の違い|コスト・納期・柔軟性で選ぶならテント倉庫
倉庫を新設・増設する際、多くの企業が悩むのが「テント倉庫とプレハブ倉庫のどちらを選ぶべきか」 という点です。 どちらにも特性があり用途によって向き不向きが大きく変わります。前編となる本記事では、テント倉庫が特に優れている「コスト」「納期」「柔軟性」 を中心に比較します。 1. 基本構造の違い(前提知識) ▼ テント倉庫とは(膜構造) ・軽量鉄骨フレームに 膜材(PVC・ポリエステル系テント生地) を張る構造 ・採光性が高く、内部が明るい ・工期が短く、コストを抑えやすい ・増築・移設が容易 で柔軟性に優れる 資材置場・荷捌き場・仮設倉庫など、幅広い用途で利用されています。 ▼ プレハブ倉庫とは(鉄骨+金属パネル構造) ・鉄骨に金属パネル(折板・サンドイッチパネル)を取り付けた建築物 ・高い断熱性・気密性・防犯性を持つ ・恒久的な倉庫や事務所併設倉庫に向く ※後編で詳しく解説します。 2. コスト比較 — 初期費用を抑えるならテント倉庫 ▼ テント倉庫(安い) ・膜材は金属パネルより材料費が安い ・基礎工事も簡易で済むことが多い→ 予算を抑えたい企業に最適 ▼ プレハブ倉庫(高くなりがち) 性能が高い分、鉄骨・パネル・基礎すべてが本格的になり、初期投資は大きくなる傾向があります。 ▼ ランニングコスト ・テント倉庫:膜材の張替えが必要(5〜15年) ・プレハブ:長寿命だがイニシャルコスト高め 「初期費用を抑えたい場合」にはテント倉庫が最有力です。 3. 納期の違い — 早く使いたいならテント倉庫 ▼ テント倉庫:非常に短工期 ・基礎工事が軽い ・膜材・鉄骨の製作期間が短い ・現場施工もスピーディー → 急ぎの倉庫設置に対応しやすい 「すぐ使いたい」「繁忙期だけ急遽増設したい」といったニーズに強いのが大きな特徴です。 ▼ プレハブ倉庫:設計〜施工に時間が必要 ・基礎工事は本格的 ・パネル製作に時間がかかる ・設備(電気・空調)作業が発生することも多い → 納期はテント倉庫より長いのが一般的です。 4. 移設・増築の柔軟性 — テント倉庫は圧倒的に強い ▼ テント倉庫(柔軟性が高い) ・鉄骨がボルト締結で構成されるため解体・再組立が容易 ・敷地内外への 移設 が可能 ・奥行延長・横連結などの 増築 もしやすい ・開口部変更・庇追加などにも柔軟に対応 → 工場や物流現場など、「レイアウト変更が多い」「扱い物量が季節変動する」企業に最適。 ▼ プレハブ倉庫(変更しにくい) ・一体型構造のため 移設はほぼ不可能 ・増築には大掛かりな工事が必要 5. スパン(間口)の違い ▼ テント倉庫:スパンは30mが実用上の限界 膜材強度の関係で、間口30m程度 が最大。 ▼ プレハブ倉庫:構造次第で大スパンも可能 ※こちらは後編で詳しく扱います。 6. テント倉庫が向いている用途(まとめ) ・資材置場・荷捌き場 ・季節需要に応じた増設 ・コスト優先の倉庫 ・急ぎの倉庫設置 ・フォークリフト動線を重視する現場 ・仮設倉庫を柔軟に運用したい場合 7. 後編のご案内 断熱性・防犯性・耐候性といった 「建物としての性能」 ではプレハブ倉庫に大きな強みがあります。 → 後編では、プレハブが優位な性能面を詳しく解説します。 【後編】テント倉庫とプレハブ倉庫の違い|断熱・耐候性・防犯性で選ぶならプレハブ倉庫 -
2025.12.04
コラム
テント倉庫と税務について
テント倉庫をご検討いただくお客様から、「テント倉庫には税金がかかりますか?」というご質問をよくいただきます。 テント倉庫は建築確認が必要となる建築物に該当するため、固定資産税の対象となります。 ただし、一定の条件を満たす場合、2027年(令和9年)3月31日まで適用されている『中小企業経営強化税制』による優遇措置を受けることができます。 ■ 中小企業経営強化税制とは? 企業の設備投資を後押しするために設けられた制度で、対象設備を取得すると 「即時償却」または「税額控除(10%/資本金3,000万円超の法人は7%)」のいずれかを選択して受けることができます。 テント倉庫本体だけでなく、 ・庇テント ・オーニング ・間仕切カーテン などの膜体製品も、一定の要件を満たすことで制度の対象となります。 対象となる設備は「施工・設置を含めて60万円以上のもの」です。 この税制は実際に広く活用されており、弊社のお客様でも数件ご利用いただいた実績がございます。対象になるかどうかは設備内容によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。 ■ 申請に必要な準備 税制優遇を受けるためには、次の手続きが必要です。 ①「経営力向上計画」を策定 設備の導入目的・効果などを記載し、申請書を作成します。 ② 経済産業大臣の「確認書」(認定)を取得 計画を申請し、認定を受けることで初めて税制優遇を利用できます。 ③ 工業会証明書の取得 テント倉庫や膜体製品は、“生産性向上設備”として要件を満たすことが多く、申請には工業会証明書が必要となります。 弊社では対象製品について、工業会証明書の発行手続きを行っています。 これらの申請と確認が設備の設置前に完了していることが必要となります。 ■ 導入をご検討中の方へ 中小企業経営強化税制は2027年(令和9年)3月31日までの期間限定です。 制度を活用することでテント倉庫・膜体製品の導入コストを大きく抑えられる可能性があります。 税制適用の判断や申請書類の作成は、お客様の税理士・会計士の先生とご相談いただくことでスムーズに進められます。 弊社では、対象製品に関する工業会証明書の発行など、設備導入に必要なサポートを行っています。 ぜひこの機会にご検討ください。 詳細は、中小企業庁の公式ページをご確認ください。 中小企業経営強化税制 -中小企業等経営強化法- 経営力向上計画 策定の手引き -
2025.06.20
コラム
アイボリーとグリーンのテントはどちらが結露しやすいでしょう?
先日上屋テント(側面の壁が一部ないタイプのテント)をお使いのお客様から、白とグリーンのテントの結露がひどいとのご相談がありました。お話を聞くと、片方の色のみ結露がひどいというのです。テントは別棟ではなく画像ように一つのテントの途中から色が変わっています。(画像はAIで作ったものですのでちょっと変です・・)皆さんはどちらの色のテント生地に結露が発生したと思いますか? 答えはグリーンの真下の結露により水が落ちていました。予想と合ってましたか?私はアイボリーの方が涼しいというイメージでしたのでイコール、シートの温度も低くアイボリーの方に結露が出ると思ったのですが、実際は違いました。お客様の方でもサーモチェックをしていただいて、冬場の朝方に計測をすると明らかにアイボリーよりもグリーンの方が温度が低かったそうです。同じメーカーの同じ商品で、ただ色が違うだけでなぜこんなに結果が違うのか、、理由は端的に言えば緑色の方が暗色であり、夜間の放射冷却の影響を受けやすい傾向があるからだそうです。ご存じでしたか?個人的には感覚と真逆の現象でとても不思議な感覚です。 すべてアイボリーであれば結露は起きないのか?というと湿気を含んだ空気が冷やされ露点を下回れば同じ結果となりますので、やはりまずは湿気を含んだ空気をテントに入れないというのが最大のポイントです。ちなみに結露に困っておられる方におすすめする対策は以下です。 1.天井に結露防止用の内張を設置 2.シーリングファンによる空気の攪拌 3.湿度の高い空気の侵入経路の遮断 一番確実なのは1番かと思いますが、結露防止用の内張をつけるとどうしても内部は暗くなります。せっかくアイボリーを使っても少しメリットは下がってしまいます。ただ、壁面を覆っていないのであればそちらからの光で日中は荷さばき作業可能な明るさは確保されます。最近ではアルミ素材の内張によって外部からの輻射熱を塞ぎ日陰をより涼しくすることもできます。ご使用される状況に応じて改善方法のご提案もできますので、もしお悩みの方は是非お問い合わせください。 -
2025.01.27
コラム
ビニールカーテンのばたつきを解決!強風対策の設備5選
ビニールカーテンは、工場や倉庫、作業現場での効率的な間仕切りとして大変便利な設備です。しかし、強風が吹き込む現場では、「カーテンがばたつく」という思わぬ問題が発生することも。 些細な問題に聞こえるかもしれませんが、まともに開閉がこれらの課題は設備選定時に見落とされがちですが、後になって大きな問題となるケースも少なくありません。 特に初めて設備を導入する方や、現在の環境改善を検討している方は、事前に対策をよく調べておくことが重要です。適切な対策を選ぶことで、カーテンの耐久性向上やコスト削減だけでなく、快適な作業環境の実現につながります。この記事では、ビニールカーテンのばたつき問題を解消するための設備をご紹介!事前に知っておくべきポイントと検討するべき設備を解説しますので、導入前の参考にぜひご活用ください。 設備導入前に知っておくべきポイント ビニールカーテンを導入する際、現場の環境を正確に把握し、適切な設備を選ぶことが成功のカギです。 業者のサポートはもちろん重要ですが、現場環境を最もよく知るのはあなた自身。業者とのやり取りをスムーズに進め、最適な提案を受けるためには、事前に知っておくべきポイントを押さえることが大切です。 ここでは、トラブルを未然に防ぎ、満足度の高い設備導入を実現するための2つの重要なポイントをご紹介します。 1. 現場の風環境を把握する 風の影響を正確に見極めることが、ばたつき防止の第一歩です。 現場の風環境を理解することで、業者に対して具体的な要望を伝えやすくなります。以下の3つの視点を事前に確認しておきましょう。 風の入り口や抜け道をチェック 工場や倉庫のレイアウトによって、風が吹き込む方向や強さは大きく異なります。たとえば、作業エリアの広さ、風が抜けやすい動線などを確認してください。特に、風が集中して吹き込むエリアでは、強風に耐えられる設備が必要になります。 開口部の大きさを確認 開口部が大きければ大きいほど、カーテンのばたつきは大きくなります。 たとえば、大型倉庫の出入り口や、トラックが通る大開口スペースでは、安定性の高いカーテンが必須です。 季節風を考慮する 冬場に特定の方向から強風が吹く地域では、特に意識する必要があります。過去の経験から把握しておくと適切な選定がしやすくなります。 2. 開閉頻度と作業性を考える 高頻度で開閉が必要な現場では、開け閉めの力が少ない設備の方がよいかもしれません。 開閉が少ない場合は、強度の高いスライドカーテンや、半固定にできるグランドフックなども検討の余地があります。 ビニールカーテンのばたつき防止対策 ビニールカーテンが強風によってばたつくのを防ぐには、環境や用途に応じた設備選定が重要です。以下に、現場の条件に適したばたつき防止のための具体的な方法を6つご紹介します。 (1) タッセルで固定する方法 カーテンを側面からタッセルで巻くことで、カーテンをオープンにした状態のばたつきを抑えることができます。既に設営済のカーテンでも簡単に取り付けられます。 (2) ウェイトチェーンの利用 カーテンの裾にウェイトチェーンを取り付けることで、風による動きを抑えます。チェーンの重さを調整することで、カーテンの安定性を高めることが可能です。 (3) グランドフックの利用 頻繁に開閉しないカーテンには、地面に取り付けたフックを使用し、カラビナなどでしっかり固定する方法が有効です。この方法により、強風時のカーテンの動きを最小限に抑え、安定性を向上させることができます。 (4) 芯材カーテンの導入 カーテンに芯材を入れることで、剛性が増し、安定性が格段に向上します。また、落としピンを併用することで、カーテンを閉じた状態で風に煽られにくくすることができます。この方法は、耐久性を求める現場に最適です。 (5) スライドカーテンの導入 ジャバラ状のスライドカーテンは、芯材にXバーを追加することで剛性を高め、強風でも形状を保ちやすくなります。特に大型カーテンでその効果を発揮し、さらにボルトローラーを採用することで開閉操作もスムーズに行えます。 ビニールカーテンのばたつき防止が必要な理由 騒音の軽減 ビニールカーテンがばたつくと、強風のたびに大きな音が発生し、作業環境の騒音レベルが上昇します。この騒音は作業員にとってストレスとなり、集中力の低下や業務効率の悪化を招く原因となります。ばたつきを防止することで、静かで快適な作業環境を維持でき、作業員の満足度とパフォーマンスの向上につながります。 カーテンの耐久性向上 強風によるばたつきは、カーテンの素材に余計な負荷をかけ、摩耗や損傷を引き起こします。この状態が続くと、破れや裂け目が生じやすくなり、修理や交換の頻度が増加します。ばたつき防止対策を行うことで、カーテンの寿命を延ばし、維持管理にかかるコストを削減できます。特に、耐久性を求める現場では不可欠な対策です。 ビニールカーテン以外の手段 強風対策として、そもそもビニールカーテンを採用しないという選択肢も検討できます。ビニールカーテンは透過性が高く、採光性や視認性に優れていることが大きなメリットですが、現場の状況によっては他の手段が適している場合もあります。以下に、ビニールカーテンに代わる代表的な方法をご紹介します。 ・メッシュ生地を採用する 強風が通り抜ける「メッシュ生地」を用いることで、風圧を大幅に軽減することができます。完全に密閉することはできませんが、意外にも雨風をある程度防ぐことが可能です。また、通気性を確保しながら作業環境を快適に保つため、特に風通しを必要とする現場で有効です。 ・引戸の設置 ビニールカーテンに比べると、引戸は形状の自由度が制限されますが、その分耐久性や安定性に優れています。強風の影響をほとんど受けず、開閉の際も力を要しないため、頻繁に使用する開口部には最適です。また、引戸はしっかりと固定できるため、防音や防塵効果も高まります。 ビニールカーテンは周囲の環境と設備選択が重要 ビニールカーテンの設置は、周囲の環境や用途に合わせた設備選択が成功のカギです。特に強風によるばたつきは、作業効率や快適性を損なうだけでなく、長期的なコストにも影響を与えます。適切な対策を講じることで、カーテンの耐久性を向上させ、静かで快適な作業環境を維持することが可能です。 また、場合によってはビニールカーテン以外の選択肢を検討することも、最適な解決策につながるかもしれません。周囲の風環境や開閉頻度をしっかりと把握し、自社の現場に最も適した設備を選ぶことが重要です。 タカダ創美では、長年の経験と豊富な実績をもとに、お客様の現場環境に最適なソリューションをご提案しています。現場の状況に応じたカスタマイズや、具体的な問題解決のご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。 -
2025.01.01
コラム
謹賀新年
あけましておめでとうございます 皆様には 健やかに新春を迎えられたことと お慶び申し上げます 旧年中は ひとかたならぬご厚情をいただき ありがとうございます 本年も 変わらぬお引き立ての程 よろしくお願い申し上げます 皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます -
2024.11.14
コラム
テント倉庫 張替え時の注意点
テント倉庫の張替えや修理の際の注意点 テント倉庫の張り替え作業において問題となるのが、倉庫内にある荷物です。 すべての荷物を移動していただけると、作業はスムーズに進みます。 しかし、すべての荷物を動かす事が難しい場合がほとんどです。 その場合は、作業車が通れる程度に中央部分を開けていただければ大丈夫です。 また、外側はテント倉庫周囲に脚立を立てるためのスペースを確保していただければ、問題なく作業を進めることが可能です。 ちなみに、張替え作業は2日~3日程度かかります。(当日の現場スタッフの人数や、天候によって左右されます) 雨天時は現場スタッフの安全確保が出来ない事と、倉庫内の荷物を濡らす事になる為、延期させていただく事が多いです。 -
2024.07.05
コラム
テント倉庫用 遮熱シートの実力
梅雨のさなかなはずですが、連日暑い日が続いています。弊社所在地の岐阜県養老郡でも本日(7月5日)は37度の予報で路面の温度計は38度を計測していました。先日、現在開催中のウルトラマックスクールキャンペーンを利用したテントの倉庫の張替えをさせていただきました。その隣に丁度同じサイズのグリーンのテント倉庫がありましたので、温度の比較をさせていただきました。下記の絵のような環境なので、W6☓L10☓H4のサイズで正面はカーテンでオープンなっています。 温度の測定は下記の3箇所で行いました。結論からいうとウルトラマックスクールのほうが3℃気温が低くなるという結果となりました。(風通しの良い庇の下は、地表近く、タイルの上での測定のため若干気温が低く出ている可能性があります) 風通しの良い庇下 ウルトラマックスクール ハリケーン グリーン色 比較対象として選んだハリケーンというテント倉庫生地はグリーン色だったこともあり、蓄熱しやすい傾向にはあります。3℃というとそれほどでもないのかな?という気もしますが、体感ではっきりと温度の差がわかる違いがありました。風通しの良い庇の下での気温との比較が5℃近くあるからか、ハリケーンの倉庫ではムッとするような暑さを感じました。ウルトラマックスクールの倉庫では違和感はあまりありませんでしたので、外気温との差も快適さを感じる大きな部分かもしれません。今回は比較的入口に近くの空気が入れ替わる場所で測定しましたが、テント倉庫の奥、風を感じない場所ではかなりの温度差を感じました。 メーカーのカタログ値では最大4℃ほど違うとの記載がありますが、今回実測、体感した限りでは間違いないように思います。まだまだ暑い日は続きます。正直な所、テント倉庫の欠点である暑さがぐっと押さえられて、膜体の寿命が通常よりも2年伸びるというのは破格の性能とコスパで、なおかつ通常品と同価格というのは今後ないと思います。ウルトラマックスクールのキャンペーンは9月までとなりますので、ぜひテント倉庫の新設、張替えをご検討の方は、この機会をご活用いただければ、というよりビッグチャンスだと思います!
CATEGORY
選択してください
ARCHIVE
選択してください
- 2026年1月 (2)
- 2025年12月 (4)
- 2025年8月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年8月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (1)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (7)
- 2020年5月 (4)
- 2020年4月 (4)
- 2020年2月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年10月 (3)