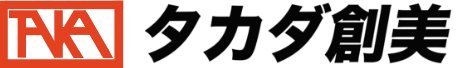NEWS & COLUMN
お知らせ&コラム
-
2025.12.15
コラム
【後編】テント倉庫とプレハブ倉庫の違い|断熱・耐候性・防犯性で選ぶならプレハブ倉庫
前編では、テント倉庫が強い「コスト・納期・柔軟性」について解説しました。後編となる本記事では、プレハブ倉庫が優れている性能面 を中心に比較します。 1. プレハブ倉庫の基本構造(おさらい) ・鉄骨に金属パネル(折板・サンドイッチパネル)を取り付けた構造 ・高い耐風性・耐雪性・断熱性・防犯性を持つ ・建築基準法の建物として扱われ、恒久利用に最適 一方のテント倉庫は膜材による簡易構造で、柔軟性・コスト性能が高い反面、 断熱・防犯性では劣ります。 2. 断熱性の違い — 温度管理が必要ならプレハブ ▼ テント倉庫(標準では断熱が弱い) ・膜材1枚構造のため外気温の影響を受けやすい ・夏場の内部温度が上がりやすい ・冬は冷え込みやすい ※遮熱膜材・内張りなどのオプションで改善可能です。 ▼ プレハブ倉庫(断熱性能が非常に高い) ・ウレタン入りサンドイッチパネル ・断熱屋根パネル これらにより、 ・暑さの侵入を抑えやすい ・冬場の暖房効率が高い ・全体的な温度管理が容易 食品・精密部品・化学製品など、温度管理が必要な倉庫はほぼプレハブ一択です。 3. 耐候性 — 風・雨・雪に対して強いのはプレハブ ▼ テント倉庫 テント倉庫は軽量鉄骨と膜材を組み合わせた構造で、地域の風荷重・雪荷重に合わせた設計によって必要な耐候性能を確保できます。 ・仕様や膜材の選択によって、風・雪への対応が可能 ・膜材は経年で劣化するため、定期的な張替えで性能を維持 ・柔軟な膜材の特性上、強風時に動きが出ることもあるが、構造上の想定範囲 用途に応じて性能を調整できるのが、テント倉庫の特徴です。 ▼ プレハブ倉庫:構造的に耐候性能が高い プレハブ倉庫は、鉄骨に金属パネルを組み合わせた建築物で、構造自体が“風・雨・雪”への耐性を高めやすい点が特徴です。 ・鉄骨フレームが強固で、外壁パネルも高い剛性を持つ ・気密性・遮水性に優れ、外気の影響を受けにくい ・積雪地域や強風地域など、環境条件が厳しい場所でも採用されやすい(※必要に応じて地域の基準に沿った構造検討が行われます) こうした構造上の特性から、長期利用を前提とした恒久的な倉庫や、屋内環境を安定させたい用途に向いています。 4. 防犯性 — 決定的な違い ▼ テント倉庫の弱点 膜材は一定の強度はあるものの、刃物で切られてしまう という構造上の弱点があります。 高価物保管には不向きで、防犯カメラや赤外線センサーの追加が必須になるケースもあります。 ▼ プレハブ倉庫(防犯に非常に強い) ・外壁が金属製 ・侵入には工具+大きな音が必要 ・建物としての“固さ”がある → 防犯性能はプレハブが圧倒的に高い 5. 用途別の最適な選択(性能面を重視する場合) ▼ プレハブ倉庫が向いている用途 ・温度管理の必要な倉庫(食品・精密機器など) ・高価物保管 ・防犯を重視する現場 ・台風・積雪などの気象リスクが高い地域 ・事務所併設施設 6. まとめ — 性能面を重視するならプレハブ倉庫 ・断熱性:プレハブが圧倒的 ・耐候性:建築物として高いレベル ・防犯性:金属パネルで侵入が困難 ・長期利用:長寿命で維持しやすい 総合的に、性能・耐久・防犯まで求めるならプレハブ倉庫が最適 といえます。 倉庫設置をご検討中の企業様へ 本記事が倉庫選びの検討にあたって参考になれば幸いです。 → 前編では、テント倉庫が優位な面を詳しく解説しています。 【前編】テント倉庫とプレハブ倉庫の違い|コスト・納期・柔軟性で選ぶならテント倉庫 テント倉庫の導入をご検討の際は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。用途・予算・納期に合わせ、最適なプランをご提案いたします。 -
2025.12.15
コラム
【前編】テント倉庫とプレハブ倉庫の違い|コスト・納期・柔軟性で選ぶならテント倉庫
倉庫を新設・増設する際、多くの企業が悩むのが「テント倉庫とプレハブ倉庫のどちらを選ぶべきか」 という点です。 どちらにも特性があり用途によって向き不向きが大きく変わります。前編となる本記事では、テント倉庫が特に優れている「コスト」「納期」「柔軟性」 を中心に比較します。 1. 基本構造の違い(前提知識) ▼ テント倉庫とは(膜構造) ・軽量鉄骨フレームに 膜材(PVC・ポリエステル系テント生地) を張る構造 ・採光性が高く、内部が明るい ・工期が短く、コストを抑えやすい ・増築・移設が容易 で柔軟性に優れる 資材置場・荷捌き場・仮設倉庫など、幅広い用途で利用されています。 ▼ プレハブ倉庫とは(鉄骨+金属パネル構造) ・鉄骨に金属パネル(折板・サンドイッチパネル)を取り付けた建築物 ・高い断熱性・気密性・防犯性を持つ ・恒久的な倉庫や事務所併設倉庫に向く ※後編で詳しく解説します。 2. コスト比較 — 初期費用を抑えるならテント倉庫 ▼ テント倉庫(安い) ・膜材は金属パネルより材料費が安い ・基礎工事も簡易で済むことが多い→ 予算を抑えたい企業に最適 ▼ プレハブ倉庫(高くなりがち) 性能が高い分、鉄骨・パネル・基礎すべてが本格的になり、初期投資は大きくなる傾向があります。 ▼ ランニングコスト ・テント倉庫:膜材の張替えが必要(5〜15年) ・プレハブ:長寿命だがイニシャルコスト高め 「初期費用を抑えたい場合」にはテント倉庫が最有力です。 3. 納期の違い — 早く使いたいならテント倉庫 ▼ テント倉庫:非常に短工期 ・基礎工事が軽い ・膜材・鉄骨の製作期間が短い ・現場施工もスピーディー → 急ぎの倉庫設置に対応しやすい 「すぐ使いたい」「繁忙期だけ急遽増設したい」といったニーズに強いのが大きな特徴です。 ▼ プレハブ倉庫:設計〜施工に時間が必要 ・基礎工事は本格的 ・パネル製作に時間がかかる ・設備(電気・空調)作業が発生することも多い → 納期はテント倉庫より長いのが一般的です。 4. 移設・増築の柔軟性 — テント倉庫は圧倒的に強い ▼ テント倉庫(柔軟性が高い) ・鉄骨がボルト締結で構成されるため解体・再組立が容易 ・敷地内外への 移設 が可能 ・奥行延長・横連結などの 増築 もしやすい ・開口部変更・庇追加などにも柔軟に対応 → 工場や物流現場など、「レイアウト変更が多い」「扱い物量が季節変動する」企業に最適。 ▼ プレハブ倉庫(変更しにくい) ・一体型構造のため 移設はほぼ不可能 ・増築には大掛かりな工事が必要 5. スパン(間口)の違い ▼ テント倉庫:スパンは30mが実用上の限界 膜材強度の関係で、間口30m程度 が最大。 ▼ プレハブ倉庫:構造次第で大スパンも可能 ※こちらは後編で詳しく扱います。 6. テント倉庫が向いている用途(まとめ) ・資材置場・荷捌き場 ・季節需要に応じた増設 ・コスト優先の倉庫 ・急ぎの倉庫設置 ・フォークリフト動線を重視する現場 ・仮設倉庫を柔軟に運用したい場合 7. 後編のご案内 断熱性・防犯性・耐候性といった 「建物としての性能」 ではプレハブ倉庫に大きな強みがあります。 → 後編では、プレハブが優位な性能面を詳しく解説します。 【後編】テント倉庫とプレハブ倉庫の違い|断熱・耐候性・防犯性で選ぶならプレハブ倉庫 -
2025.12.04
コラム
テント倉庫と税務について
テント倉庫をご検討いただくお客様から、「テント倉庫には税金がかかりますか?」というご質問をよくいただきます。 テント倉庫は建築確認が必要となる建築物に該当するため、固定資産税の対象となります。 ただし、一定の条件を満たす場合、2027年(令和9年)3月31日まで適用されている『中小企業経営強化税制』による優遇措置を受けることができます。 ■ 中小企業経営強化税制とは? 企業の設備投資を後押しするために設けられた制度で、対象設備を取得すると 「即時償却」または「税額控除(10%/資本金3,000万円超の法人は7%)」のいずれかを選択して受けることができます。 テント倉庫本体だけでなく、 ・庇テント ・オーニング ・間仕切カーテン などの膜体製品も、一定の要件を満たすことで制度の対象となります。 対象となる設備は「施工・設置を含めて60万円以上のもの」です。 この税制は実際に広く活用されており、弊社のお客様でも数件ご利用いただいた実績がございます。対象になるかどうかは設備内容によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。 ■ 申請に必要な準備 税制優遇を受けるためには、次の手続きが必要です。 ①「経営力向上計画」を策定 設備の導入目的・効果などを記載し、申請書を作成します。 ② 経済産業大臣の「確認書」(認定)を取得 計画を申請し、認定を受けることで初めて税制優遇を利用できます。 ③ 工業会証明書の取得 テント倉庫や膜体製品は、“生産性向上設備”として要件を満たすことが多く、申請には工業会証明書が必要となります。 弊社では対象製品について、工業会証明書の発行手続きを行っています。 これらの申請と確認が設備の設置前に完了していることが必要となります。 ■ 導入をご検討中の方へ 中小企業経営強化税制は2027年(令和9年)3月31日までの期間限定です。 制度を活用することでテント倉庫・膜体製品の導入コストを大きく抑えられる可能性があります。 税制適用の判断や申請書類の作成は、お客様の税理士・会計士の先生とご相談いただくことでスムーズに進められます。 弊社では、対象製品に関する工業会証明書の発行など、設備導入に必要なサポートを行っています。 ぜひこの機会にご検討ください。 詳細は、中小企業庁の公式ページをご確認ください。 中小企業経営強化税制 -中小企業等経営強化法- 経営力向上計画 策定の手引き -
2025.06.20
コラム
アイボリーとグリーンのテントはどちらが結露しやすいでしょう?
先日上屋テント(側面の壁が一部ないタイプのテント)をお使いのお客様から、白とグリーンのテントの結露がひどいとのご相談がありました。お話を聞くと、片方の色のみ結露がひどいというのです。テントは別棟ではなく画像ように一つのテントの途中から色が変わっています。(画像はAIで作ったものですのでちょっと変です・・)皆さんはどちらの色のテント生地に結露が発生したと思いますか? 答えはグリーンの真下の結露により水が落ちていました。予想と合ってましたか?私はアイボリーの方が涼しいというイメージでしたのでイコール、シートの温度も低くアイボリーの方に結露が出ると思ったのですが、実際は違いました。お客様の方でもサーモチェックをしていただいて、冬場の朝方に計測をすると明らかにアイボリーよりもグリーンの方が温度が低かったそうです。同じメーカーの同じ商品で、ただ色が違うだけでなぜこんなに結果が違うのか、、理由は端的に言えば緑色の方が暗色であり、夜間の放射冷却の影響を受けやすい傾向があるからだそうです。ご存じでしたか?個人的には感覚と真逆の現象でとても不思議な感覚です。 すべてアイボリーであれば結露は起きないのか?というと湿気を含んだ空気が冷やされ露点を下回れば同じ結果となりますので、やはりまずは湿気を含んだ空気をテントに入れないというのが最大のポイントです。ちなみに結露に困っておられる方におすすめする対策は以下です。 1.天井に結露防止用の内張を設置 2.シーリングファンによる空気の攪拌 3.湿度の高い空気の侵入経路の遮断 一番確実なのは1番かと思いますが、結露防止用の内張をつけるとどうしても内部は暗くなります。せっかくアイボリーを使っても少しメリットは下がってしまいます。ただ、壁面を覆っていないのであればそちらからの光で日中は荷さばき作業可能な明るさは確保されます。最近ではアルミ素材の内張によって外部からの輻射熱を塞ぎ日陰をより涼しくすることもできます。ご使用される状況に応じて改善方法のご提案もできますので、もしお悩みの方は是非お問い合わせください。 -
2024.11.14
コラム
テント倉庫 張替え時の注意点
テント倉庫の張替えや修理の際の注意点 テント倉庫の張り替え作業において問題となるのが、倉庫内にある荷物です。 すべての荷物を移動していただけると、作業はスムーズに進みます。 しかし、すべての荷物を動かす事が難しい場合がほとんどです。 その場合は、作業車が通れる程度に中央部分を開けていただければ大丈夫です。 また、外側はテント倉庫周囲に脚立を立てるためのスペースを確保していただければ、問題なく作業を進めることが可能です。 ちなみに、張替え作業は2日~3日程度かかります。(当日の現場スタッフの人数や、天候によって左右されます) 雨天時は現場スタッフの安全確保が出来ない事と、倉庫内の荷物を濡らす事になる為、延期させていただく事が多いです。 -
2024.07.05
コラム
テント倉庫用 遮熱シートの実力
梅雨のさなかなはずですが、連日暑い日が続いています。弊社所在地の岐阜県養老郡でも本日(7月5日)は37度の予報で路面の温度計は38度を計測していました。先日、現在開催中のウルトラマックスクールキャンペーンを利用したテントの倉庫の張替えをさせていただきました。その隣に丁度同じサイズのグリーンのテント倉庫がありましたので、温度の比較をさせていただきました。下記の絵のような環境なので、W6☓L10☓H4のサイズで正面はカーテンでオープンなっています。 温度の測定は下記の3箇所で行いました。結論からいうとウルトラマックスクールのほうが3℃気温が低くなるという結果となりました。(風通しの良い庇の下は、地表近く、タイルの上での測定のため若干気温が低く出ている可能性があります) 風通しの良い庇下 ウルトラマックスクール ハリケーン グリーン色 比較対象として選んだハリケーンというテント倉庫生地はグリーン色だったこともあり、蓄熱しやすい傾向にはあります。3℃というとそれほどでもないのかな?という気もしますが、体感ではっきりと温度の差がわかる違いがありました。風通しの良い庇の下での気温との比較が5℃近くあるからか、ハリケーンの倉庫ではムッとするような暑さを感じました。ウルトラマックスクールの倉庫では違和感はあまりありませんでしたので、外気温との差も快適さを感じる大きな部分かもしれません。今回は比較的入口に近くの空気が入れ替わる場所で測定しましたが、テント倉庫の奥、風を感じない場所ではかなりの温度差を感じました。 メーカーのカタログ値では最大4℃ほど違うとの記載がありますが、今回実測、体感した限りでは間違いないように思います。まだまだ暑い日は続きます。正直な所、テント倉庫の欠点である暑さがぐっと押さえられて、膜体の寿命が通常よりも2年伸びるというのは破格の性能とコスパで、なおかつ通常品と同価格というのは今後ないと思います。ウルトラマックスクールのキャンペーンは9月までとなりますので、ぜひテント倉庫の新設、張替えをご検討の方は、この機会をご活用いただければ、というよりビッグチャンスだと思います! -
2022.02.01
コラム
テント倉庫の張替えのタイミング
上記の写真、昨年末に弊社が張替えさせていただいたテントの、張替え前のものですが、何年前だと思いますか? ある日弊社に「御社で建てたテントを張り替えてほしいのですが・・・」とのお問い合わせをいただき調べてみると、なんと27年前に弊社が設置させていただいたテントでした。27年前、、弊社若手社員よりも圧倒的年上の物件で、社員一同どよめいてしまいました。 では一般的に現在のテント生地は27年も持つのかと言われますと、残念なことですが持たないと言わざるを得ません。日本の環境変化も顕著ですが、生地に含まれている成分についても現在は手に入らないもの、環境を配慮し使えないものもあり、一般的なテント倉庫用の生地は7年耐久、一つランクの上がったテントは10年耐久、最長の記載のあるものでも15年となっております。ただ、現実的には7年耐久のものは10年程度持つことが多いようですが、風が強いところ、日射を長く受ける場所、鳥獣が危害を加える場所(田舎では現実にあります)とうではやはり短くなる可能性があります。 ただ、殆どのテントについては、破れる際に前兆があります、軽微な雨漏りや下から見た際の光の漏れなど、そういったものを見逃さずケアし、備えることで支障が少なく張り替える事が可能ですので、見逃さずお問い合わせいただければと思います。また、そういった背景もあり、10年耐久の素材を使用したお見積もりもご提案をさせていただいております。長い目で見れば必ずお客様の利益になることですし、持続可能な社会を目指すためにも末永くご使用いただければと思っております。 ちなみに、この27年前のテント倉庫は弊社に青焼きの図面が残されていました。残しておける土地がある田舎企業の良いところがでました。それよりも何よりも、27年前に施工させていただいた弊社をお客様がご記憶いただけていたたことが、これ以上なく嬉しいことでした。次は何年後かわかりませんが、またご依頼いただけるよう精進したいと思います。 -
2020.12.07
コラム
大雪にも耐えられるテント倉庫とは
たくさん雪が降る地域にテント倉庫を建てたいけれど、強度は大丈夫? 稀にそのような問い合わせを頂きます。多雪地域にも耐えられるテント倉庫・テントハウスは積雪テント・耐雪テントと呼ばれており、鉄骨の強度や屋根などに一工夫あります。そこで今回は積雪テントについて紹介します。 積雪テントとは 積雪テントとは上記で軽くふれたように、大雪にも耐えられるような設計や、使いやすい配慮を施したものになります。積雪テントのポイントは下記の4つです。 ・フレーム・生地の強度 ・屋根の傾斜 ・開口の向き・種類 ・周囲のスペース フレーム・生地の強度 多雪地域にも耐えられるよう、積雪テントはフレーム・生地の強度が強化されています。テント倉庫の設計は荷重、風、積雪荷重などによって求められる強度を計算しており、多雪地域では積雪1m以上にも耐えられるよう設計しなくてはなりません。そのため、鉄骨を太く・スパンを短く配置し、屋根の上に降り積もる雪に耐えられるようになっています。 また弊社では、通常よりも丈夫な生地の採用を勧めております。多雪地域に設営されるテント倉庫は雪や風など過酷な状況に晒されており、生地の破れなどのリスクがどうしても高くなってしまいます。 修理や張り替えなどのメンテナンスコストを考えると、長期的にみてお得かと思います。 この施工事例はこちらから 屋根の傾斜 積雪テントは屋根に雪がなるべくたまらないよう、屋根の勾配がきつく設計されています。ちなみに弊社は岐阜県にあるため、常に積雪を意識しています。多雪地域でない通常地域でも、勾配は少々きつめな3寸(横10に対し高さ3の割合の傾斜)、多雪地域では4寸に設定しています。勾配をきつくすると、軒より上の高さが高くなります。高さに制限がある場合は、実際に運用できる天井の高さが低くなってしまいますので、積雪テントを建てる際はしっかりと確認してください。 写真の施工事例はこちらから 開口の向き・種類 風向きによって雪が溜まりやすい方角があります。そのような位置に開口を設けるのは得策ではありません。どこに溜まりやすいかはテント施工業者よりもその場で働いているお客様の方が詳しいかと思われますので、開口をどこに設けるか、その際に工場・倉庫の動線はどうなるか、しっかりとした計画が必要です。 また、開口にどのような扉を設けるかの検討も必要です。通常の引き戸ならば問題ありませんが、もし開口を大きくとるためカーテンの設営をお考えならば、ジャバラカーテンなど補強材の入っているタイプをお勧めします。 周囲のスペース 雪がどの方向に落ちるかのシミュレーションが必要です。屋根に溜まった雪が落ちる先が頻繁に利用する通路ならば、雪かきが大変になります。 雪が落ちる先を片側にしたいならば、片流れテントをお勧めします。雨や雪の流れ落ちる先を誘導できるので、悪天候時でも動線の確保が容易です。 写真の施工事例はこちらから まとめ 積雪テントは通常のテントよりも考えなければならないことが多くあります。テント業者の方としっかりお打ち合わせをして、よりよくお使い頂ければと思います。 タカダ創美でも積雪テントを承っておりますので、一度ご相談ください。 -
2020.09.09
コラム
確認申請とは?
確認申請とは? 建築物を建てる前に建物や地盤が建築基準法に適合しているか確認することを、建築確認といいます。 確認は自治体や自治体から指定を受けている民間の検査機関が行うのですが、そういった検査機関に検査を依頼するこを建築確認申請、もしくは確認申請と呼ばれています。 申請は設計事務所や施工会社が行うので、特に施主が何かをするということはありませんが、何やら難しい言葉で困惑しますね。 [gallery ids="2957"] 法令について 膜建築物について定める法令について、国土交通省告示第666号があります。これは膜建築物を一般の建築物と同様の扱いがされるよう基準を定めたものです。一方で、テント倉庫など用途を限定することで構造を簡易化しコストと納期期間を抑えたい要望もあり、これに対応するため国土交通省告示第667号による緩和処置があります。 下記は667号の適応条件の一部です。このような条件に当てはまらない膜建築物は、666号の適応範囲となります。 用途が倉庫であること。 延べ面積1,000㎡以下で階数が1であること。 軒高5m以下であること。 屋根の形式は、切妻、片流れ、又は円弧屋根面とすること。 確認申請は必要? 原則として必要となりますが、ごく小さいサイズならば確認申請が必要ない場合もございます。また、用途や大きさ、地域によっては消防設備なども必要に応じて義務付けられております。まずはご相談ください。 -
2020.08.03
コラム
テント倉庫の台風対策
テント倉庫は台風に弱い、というイメージを持たれる方は多いのではないのでしょうか。 確かに「何十年に一度」というような台風では、被害にあってもおかしくないでしょう。2018年に発生した台風21号は各地域に多くの被害を与え、弊社でも全てのお客様へ対応するのに大変お時間を頂きました。 一方で通常の台風であれば、多くのテントは問題なく耐えられることも間違いございません。メンテナンスや対策をしっかり行っていれば、多くの場合は問題なくやりすごすことができます。 今回は、テント倉庫における台風対策を紹介いたします。皆様の参考になれば幸いです。 [gallery ids="2928"] 生地の点検 台風シーズンの前に一度、テント生地の点検をされることをおすすめします。もし生地に破れがあると、その裂け目からさらに悪化する恐れがあります。事前に生地を補修して頂くことで、強風に耐えられる可能性が高くなります。 生地の張り替え 弊社では通常、10年を目途に生地の張り替えを推奨しています。劣化した生地は柔軟性を失ってパリパリになってしまい、強風に耐えることが難しくなるためです。 生地の破れが酷い箇所のみの張り替えを希望されるお客様もいらっしゃいますが、生地の劣化が酷い場合は全面張り替えを推奨しています。結果として、そちらの方が工期やコストも抑えられることが多いです。被害を出す前に張り替えを検討して頂けたら幸いです。 鉄骨の補修 何十年とテント倉庫をお使いになられている方は、一度鉄骨の確認もしたほうがようかもしれません。鉄骨には防錆加工が施されておりますが、テント生地に触れる個所などから徐々に錆が浸食していきます。また、フォークリフトなど重機の操作ミスにより破損してしまった鉄骨も要注意です。 錆転換材の塗布や欠損個所の補修を行うことで、より長くお使いいただけます。 強度の高い生地の選択 テント倉庫の発注時に、強度の高い生地を選択することも重要です。より強い台風に耐えられ、メンテナンス頻度も抑えることができます。モノの移動の手間、雨漏り等の被害を考慮すると、初期費用さえ許せば賢い選択かもしれません。 もし破れが発生してしまったら いち早くテント会社に連絡を頂ければと思います。保険が適用できる場合もございますので、併せてご相談ください。 張替え・修理のページはこちらから
CATEGORY
選択してください
ARCHIVE
選択してください
- 2026年1月 (2)
- 2025年12月 (4)
- 2025年8月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年8月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (1)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (7)
- 2020年5月 (4)
- 2020年4月 (4)
- 2020年2月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年10月 (3)